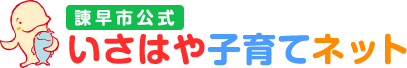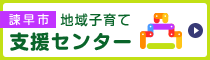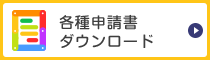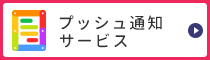公開日
最終更新日
児童手当概要
児童手当は、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者(受給者)
- 一般の受給者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
ただし、離婚前提で別居の場合は、児童と同居している人が優先される場合があります。
お問い合わせください。
※受給者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給者が諫早市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
- 施設等受給者(施設の設置者、里親等)
支給対象となる児童が入所する、市内に施設を設置する者等
支給対象児童
国内に居住する高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童
※留学等で国外に居住する場合には、支給対象となる場合があります。お問い合わせください。
支給額
|
児童の年齢 |
第1・2子 |
第3子以降 |
|
3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
|
3歳~ 高校生年代 |
10,000円 |
30,000円 |
支給予定月
原則として毎年偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)8月の支給日には、6、7月分の手当を支給します。
認定請求
出生、転入等によって新たに諫早市での受給資格が生じ、児童手当を受給する場合には、「認定請求書」の提出が必要です。
受給資格が発生した日(転入については、前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に手続をしてください。
※児童手当の支給は、申請の翌月分からになります。
※事由の発生日が月末の場合、発生日の翌日から15日以内に申請を行えば、事由発生日の翌月分から受給できます。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
額改定届
児童手当の支給対象児童が、出生等で増えた場合には、「額改定届」の提出が必要です。
受給資格が発生した日(出生日)の翌日から15日以内に手続をしてください。
※児童手当の支給は、申請の翌月分からになります。
※事由の発生日が月末の場合、発生日の翌日から15日以内に申請を行えば、事由発生日の翌月分から受給できます。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
消滅届
- 受給者が市外に転出する場合
諫早市での受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。
また、転出後に新住所地で新たに認定請求書の提出が必要です。
転出予定日の翌日から15日以内に新住所地へ認定請求書を提出してください。
- 離婚、死亡等で支給対象児童を養育しなくなった場合、または受給者が死亡した場合
児童手当の受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。
変更届
以下の変更があった方は「変更届」の提出が必要となります。変更が生じたら速やかに届け出てください。
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 市外に住民票がある配偶者との婚姻関係(離婚を含む)に変更があったとき
- 市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変更となったとき
別居監護申立書
受給者が、児童と住居を別にする場合、「別居監護申立書」を提出してください。
また、児童が市外在住の場合は、手続きの際にマイナンバーがわかるもの、又は児童の世帯全員の住民票が必要です。
手続きに必要なもの
認定請求書
- 請求者名義の振込先口座が分かるもの
〜以下は該当する方のみ必要です〜 - 医療保険の資格が確認できるもの(国保、社保、私学共済、生活保護以外の人)
- マイナンバーのわかるもの(配偶者または児童の住所が市外の人)
- その他(状況によっては、1~3以外の書類等が必要となる場合があります。)
現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
※提出が必要な方には、諫早市より5月末頃に現況届を送付いたします。
※現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が諫早市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、諫早市から提出の案内があった方
(例)支給対象児童と住民票上別居されている方
保険証が各種共済組合(私立学校教職員共済を除く)の方 など
寄附のご案内
地域における児童の健やかな育ちを支援するために、児童手当を役立てて欲しいとお考えの人は、手当の全部または一部を寄附することができます。詳しくは、子育て支援課へご確認ください。
児童手当の手続きは電子申請ができます
児童手当の申請について、電子申請も可能ですので、ご活用ください。
「認定請求書」
https://apply.e-tumo.jp/city-isahaya-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5883
「別居監護の申立書」
https://apply.e-tumo.jp/city-isahaya-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5916
「額改定請求書」
https://apply.e-tumo.jp/city-isahaya-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=8211
「監護相当・生計費の負担についての確認書」
https://apply.e-tumo.jp/city-isahaya-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5539
令和6年10月から児童手当の制度が一部変更となりました。
主な制度改正(拡充)の内容
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 所得制限の撤廃
- 支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
【制度内容の比較一覧表】
※大学生年代のお子様を第3子以降加算のカウントに含めるためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の手続きが必要です。
(多子加算の例)第1子、第2子などの数え方
21歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子、10歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は15歳のお子様と10歳のお子様となり、15歳のお子様は第2子の月額、10歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。